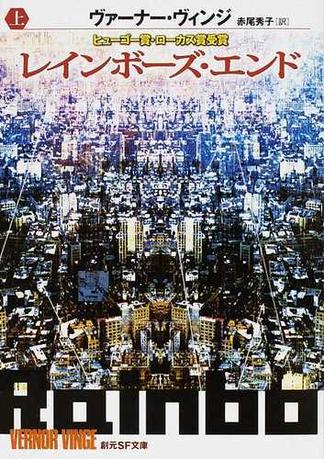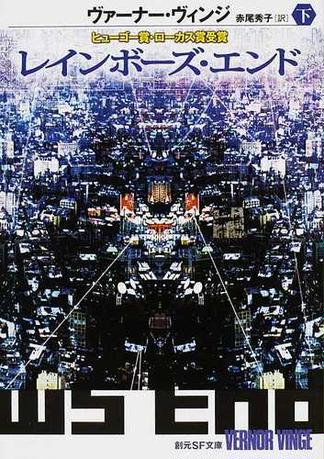『レインボーズ・エンド』(上・下)
- 著者:ヴァーナー・ヴィンジ
- 訳者:赤尾秀子
- 出版:東京創元社
- ISBN:9784488705053
- お気に入り度:★★★★☆
- 著者:ヴァーナー・ヴィンジ
- 訳者:赤尾秀子
- 出版:東京創元社
- ISBN:9784488705060
- お気に入り度:★★★★☆
『遠き神々の炎』(感想はこちら)、『最果ての銀河船団』(感想はこちらとこちら)が非常に面白かったヴァーナー・ヴィンジ。二作とも遠未来を舞台としたSFだったが、本作はうって変わって近未来を舞台としたSFだ。
舞台となっている時代は2030年代らしい。コンピュータはウェアラブル・コンピューティングというものに置き換わっている。特殊なコンタクトレンズと衣服を装着し、ちょっとした目の動きや身体の仕草で操作するだけで、バーチャルな映像を現実のものにオーバーラップして表示することができる。これらにはものによっては(値段によっては)触感さえある。肉眼で見えるものとは別のレイヤーで、いくつにも映像が重なって見える、そんな技術が社会に浸透している。この発達したウェアラブルの技術が、ある意味このSFの主役でもある。
似たような仮想現実の世界は『ゴールデン・エイジ』(感想はこちら)でも描かれていたが、選べるOSやソフトウェアに現在あるOSや企業名が使われたりしていて、本書の方がより現実味を感じさせられる。
EU諜報局は、人々をマインドコントロールすることのできる細菌兵器が、アメリカの研究施設で開発されている可能性をつかんだ。これを阻止するためにハッカーの“ウサギ”を雇って計画を立てさせた。“ウサギ”が目を付けたのは、ある中学校の職業訓練コース。ここでは成人クラスの老人達と子供達が机を並べて一緒に学んでいる授業があった。“ウサギ”はここの老人達の何人かとアフィリエイト契約を結び、研究施設に潜入できるよう、条件を整えていった。
“ウサギ”とアフィリエイト契約を結んだ一人がロバート・グー。彼の息子は海軍の中佐で、その妻は大佐という、おあつらえの人物だった。ロバートは、かつて優れた詩で名を馳せた詩人だったが、アルツハイマーを患い、新しい治療法のおかげで快復したばかりだった。けれども彼は周囲の人を絶妙のタイミングで深く傷つけることが得意な、辛辣な人物でもあった。治療のおかげではっきりした意識は取り戻したものの、昔のような詩の才能は失われてしまっていた。また、意識の朦朧としていた間に発達したウェアラブルの使い方を一から学ばなければならない。ロバートは中学生のフアン・オロスコと共同で授業の課題をこなしながら、一方で同じクラスの老人達が“ウサギ”のために行っている活動に引き込まれていった。
上巻は、老人達が馴染みの無い新しい技術を習得しようとして躍起になっている様子が描かれていて、少し辛気くさいし、SFとしていまいち面白みに欠ける。ゲームのような世界観が現実世界にオーバーラップして表示されたりするのだが、ゲームっぽい世界を文章で表現していること自体が、陳腐さを感じさせる気がする。おまけに、主人公格のロバートがなかなか嫌なやつなのだ。大人げなく孫のミリを傷つけたり、フアンや同じクラスの老人達に対しても辛辣だ。なのであまり面白いという実感がなかった。
しかし下巻になると、ロバートが少しずつ他人へ気遣いを示していく様子が描かれてくる。特にロバートがミリの命を自分の身を挺して守ろうとした様子は、当初が辛辣な人物だっただけに感動的だ。
ところで、解説を読むと“ウサギ”の存在が重要なようである。作者のヴァーナー・ヴィンジは90年代初頭に〈特異点〉についてのエッセイを発表したそうだ。〈特異点〉がどういったものなのか、言葉に聞き覚えはあってもよくわかっていないので説明は省くが、解説の向井淳氏によると、その〈特異点〉について正面から描いたのが本書ではないかということだ。ただ、“ウサギ”が本当はどういう存在だったのか、どうなってしまったのか、本書ではきちんと種明かしされていない。もしかすると今後続篇が発表されるのかもしれない。それはそれで楽しみだ。