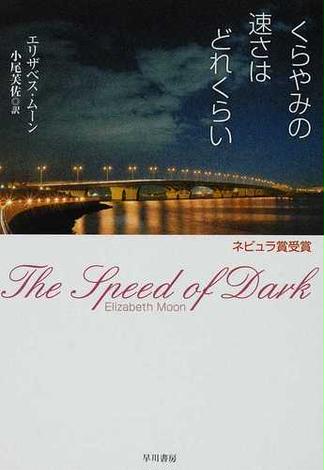『くらやみの速さはどれくらい』
- 著者:エリザベス・ムーン
- 訳者:小尾芙佐
- 出版:早川書房
- ISBN:9784150116934
- お気に入り度:★★★★☆
自閉症が治療可能となった近未来。自閉症者最後の世代であるルウは、製薬会社の仕事とフェンシングの興味をもち、困難はありつつも自分なりに充実した日々を送っていた……ある日上司から、新しい治療法の実験台になることを迫られるまでは。“光の前にはいつも闇がある。だから暗闇の方が光よりも速く進むはず”そう問いかける自閉症者ルウのこまやかな感性で語られる、感動の“21世紀版『アルジャーノンに花束を』”。
カバーより本書と『アルジャーノンに花束を』(感想はこちら)との類似は指摘しつくされているだろうから、私はむしろ、テーマはイーガン作の『万物理論』(感想はこちら)と同じだと指摘しておこう。
『万物理論』では、《自発的自閉症者協会》に属する人物の主張が衝撃的だった。彼らは脳のラマント野*1という部位を自発的に切除して、自閉症者として生きることを選択していた。自分自身のアイデンティティを自閉症であることに見いだし、より良く生きるためにラマント野の切除を選択したのだ。そして読者に「Hワード」を突きつける。何を指して「健康的」というのか、少数派として生まれついてしまったらそれは「健康的」とはみなされないのか、個々人で認識の異なる「健康的」という基準を自分の基準が正しいものと疑いもせず他人にまで押し付けるな、と。
こうしたテーマはよく似ていても、内容は大きく異なっている。本書の主人公ルウは自閉症者。彼の心情や日常が、彼の目を通してきめ細かく描かれている。私にとっては『万物理論』はベストSFのトップをぶっちぎるお気に入りだが、本書の方がわかりやすくて読みやすいので一般受けもしやすいだろう。SFを読みつけない人にも勧めやすい。自閉症の子供を持つ親などには励みになるだろう。作者自身にも自閉症の子供がいるようだ。テーマも『万物理論』よりシンプルな分、ぶれずにストレートに伝わりやすい。
ルウの目を通した世界の表現が美しい。ルウが独特の執着と興味で眺めた世界がここには描かれている。ルウが得意とするのはパターンの読み取りで、フェンシングの動作などにそれを見つけ出す。これを本人が解説するのがなるほどと思えて興味深い。私には見えない世界が広がっている。ルウは企業にも勤めていて、普通の人には見て取れないパターンを読み取り、目覚ましい成果をあげている。ただし感情が高ぶったりするとトランポリンで飛んだりしないと落ち着けない。
彼はきちんと一人で生活し、周囲に迷惑をかけてもいない。けれども、彼が自閉症者だということだけで彼を快く思わない人達は存在する。勤務先の新しい上司はルウや彼の同僚達を、自閉症を治す新薬の被験者になるよう解雇をちらつかせて脅しつける。趣味のフェンシングサークルの仲間は、自分の気のある女性が自分に冷たくすることをルウのせいにして嫌がらせをする。もちろんそんな人ばかりではなく、ルウの才能を評価し、ルウに味方してくれる人も大勢いる。そういった人達との交流が描かれている。
書体の使い方が効果的だ。通常使われる本文の書体でルウの視点を一人称で表し、違和感のある書体で自閉症ではない人々の視点を三人称で表している。この表現の仕方で、読者はルウの視点から世界を眺める。自閉症ではない人達にルウが感じる違和感が、うまく表現されているように思う。
自閉症のままでもそれなりに適応し、才能を発揮し、愛されているルウ。果たして自閉症ではなくなったルウはこれまでのルウとは違ってしまうのか。自分らしさというものがどこにあり、それはどこまで大切にすべきものなのか、考えさせられる。
『万物理論』の作者イーガンは、極端に描くことで問題を提起する。だからテーマが衝撃的で際立つのだけれど、グロテスクだし実際的ではない。イーガンはその後の作品『ディアスポラ』(感想はこちら)で、「自分らしさ」を追求して身体に改変を繰り返したあまり、極端なグループ同士では意思疎通すら不可能となってしまった人々を描いている。「自分らしさ」の追求も、究極まで突き詰めるとそうなるのだ。それでは意味が無い。
果たしてルウは何を選択し、どうなってしまうのかが本書の注目のしどころだ。結局全てのものは変化する。人も同様で、日々学んで体験し、変わってゆく。また、成長するし病気にもなるし老いていずれは死んでゆく。変わらない「自分らしさ」などは幻想にすぎない。それにこだわって「自分らしさ」を限定するよりは、変化する自分を受け入れ、どうしたらより良く生きられるかということを模索した方が良いように思う。