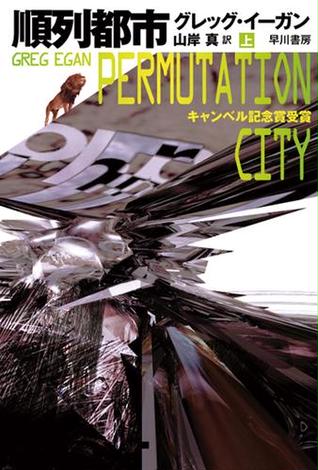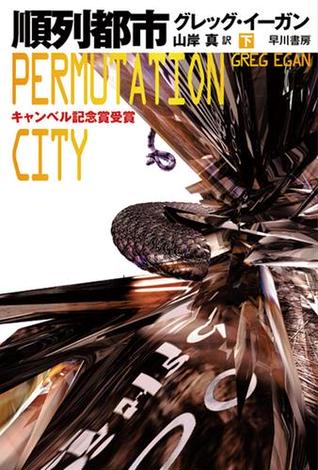『順列都市』(上・下)
- 著者:グレッグ・イーガン
- 訳者:山岸真
- 出版:早川書房
- ISBN:9784150112899
- お気に入り度:★★★★☆
記憶や人格などの情報をコンピュータに“ダウンロード”することが可能となった21世紀なかば、ソフトウェア化された意識、〈コピー〉になった富豪たちは、コンピュータが止まらないかぎり死なない存在として、世界を支配していた。その〈コピー〉たちに、たとえ宇宙が終わろうと永遠に存在しつづけられる方法があると提案する男が表れた……電脳空間の驚異と無限の可能性を描く、キャンベル記念賞、ディトマー賞受賞作
カバーより- 著者:グレッグ・イーガン
- 訳者:山岸真
- 出版:早川書房
- ISBN:9784150112905
- お気に入り度:★★★★☆
一番最初に読んだイーガンの作品。けれどもどんな内容だったかすっかり忘れていた。仮想現実の世界を扱ったSFで、何人かの登場人物が入れ替わり登場するために時間の流れなどが把握しづらく、それなりに面白かったものの分かりにくかったという記憶しかなかった。今回読み直してみて、ようやく内容がつかめた気がする。最初に読んだ時にはイーガンが初めてだったということもあり、彼の意図する所を理解していなかったのと、特に量子力学の観察者の問題が分かっていなかった*1のだと思う。
オートヴァースと呼ばれるおもちゃの宇宙モデルの世界に、マリアは新しい有機生命体を作り出すことに成功した。コンピュータ・モデルのこのオートヴァースの世界には、扱いやすいよう単純化した専用の物理法則があり、全てのものはその法則に従って動いていた。ポール・ダラムはマリアにある仕事をして欲しいと依頼して来た。オートヴァースの生命が豊かで多様化することを可能とする惑星環境と、そこで生き、高次の生命体へと進化する可能性を秘めた有機生命体の種子を、プログラミングしてほしいというのだ。しかし現実問題としてそのプログラムを走らせることが可能となるハードウェアは存在せず、現状で走らせるとなると何十億年も必要となるほどの、非現実的なものだった。だがマリアはこのプロジェクトに着手する。
このマリアの物語と並行して、〈コピー〉として目覚めたポール・ダラムの物語と、大富豪トマス・リーマンの〈コピー〉の物語と、あまり裕福ではない〈コピー〉のピーとケイトの物語が語られる。彼らは仮想現実(パッチワークVR)の中で生きている。ここでの仮想現実は、一貫性のある物理法則で動いているオートヴァースとは違い、システムを継ぎはぎ(パッチワーク)して動いているものだ。ダラムはリーマンに不死の世界の提供を約束し、ピーとケイトはリーマンによって、その世界へ自分達の〈コピー〉を密航させてもらうことになった。こうして順列都市が発進する。
改めて読み直してみると、イーガンが同じテーマを繰り返し考察していることがよくわかる。ひとつは観察者問題。『90年代SF傑作選集』(感想はこちら)の「ルミナス」でも感想に書いたけれど、未観察の宇宙を意識が観察することで、観察者の側の宇宙の法則が適用されて世界が確立する(たぶん)というものだ。「シュレディンガーの猫」は、箱の中にいる猫が生きているか死んでいるかが観察された瞬間に決まるという思考実験だったが、それが宇宙まるごとの規模で展開されているのだろう。『万物理論』と「ルミナス」もこれと同じテーマだし、『宇宙消失』は観察による確定を自在に操ることができたなら、という内容だ。
もうひとつのテーマはアイデンティティの問題。バーチャルな世界とかパラレルな世界では、自分自身のコピーを無限に作り出すことができる。それを通して「自分」とは何かをとことん突き詰めてシミュレーションしつくすのが、イーガンである。オリジナルとコピーで環境が変われば立場も変わり、他人となる。価値観や宗教、興味の対象、その時々の感情などは、バーチャルな世界ではいくらでも手を加えることができる。さらにそこに、無限に広がる可能性や偶然性が加わる。Aを選んだ自分、Bを選んだ自分、Cを選んだ自分。「自分」というものは無数に分割可能で、違う他人になる要素を無限に秘めている。これも『宇宙消失』でも『ディアスポラ』でも繰り返し考察されているテーマだ。
もうひとつ、この作品ではキリスト教の否定が大きなテーマとなっている。これが書きたくて一冊書いてしまったのではないかと思われるほど、創造主としての神を徹底的に否定してある。主人公がマリアなのもそのためだと思われる。
それにしても、後書の作品発表年を見て驚いた。『宇宙消失』1992年、本作『順列都市』1994年、『万物理論』1995年、『ディアスポラ』1997年と、これだけの力作ぞろいが短期間に書かれた上に、10年も前に書かれたものなのだ。これ以降に書かれた作品はどんなにすごいのだろうと、早く訳されることを期待してしまう。
*1:今もそういうものらしいという程度にしか分かっていないけれど